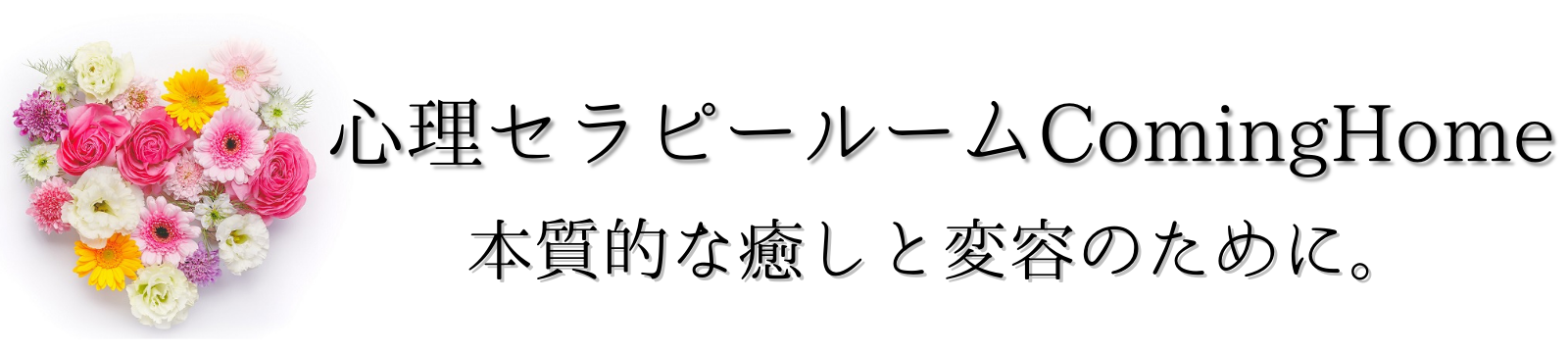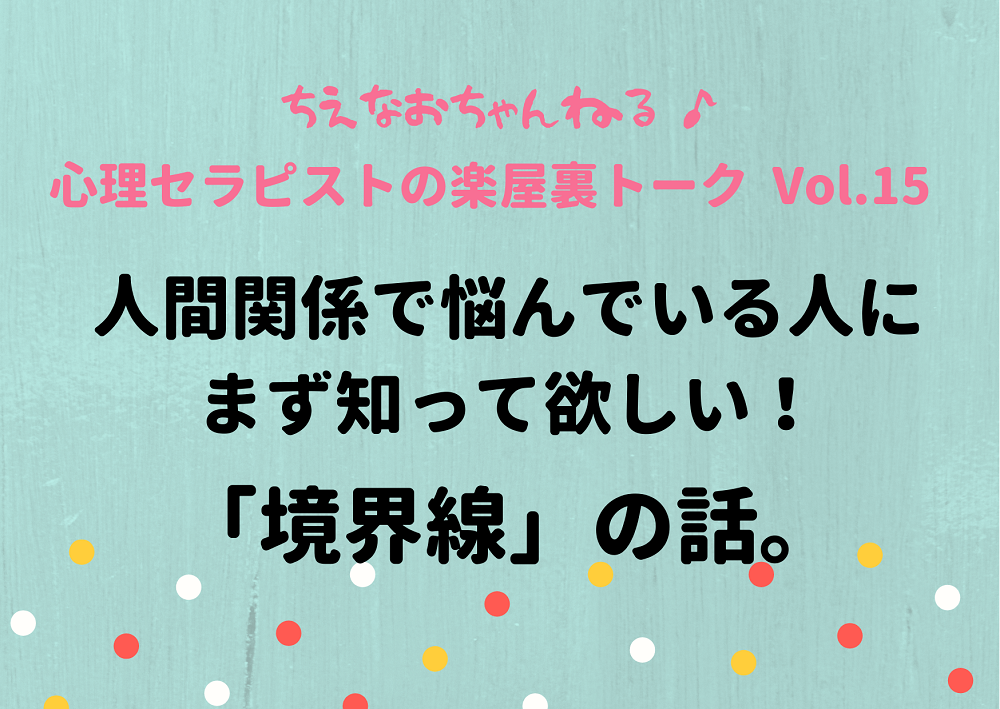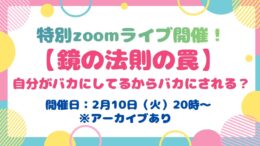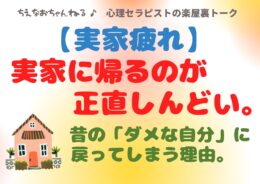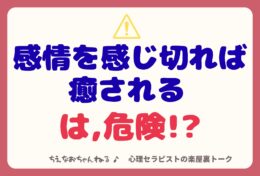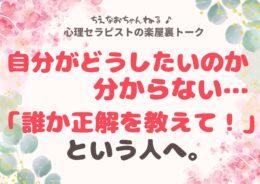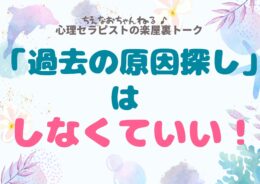人間関係って、時に大きなストレスになりますよね。
嫌だと言いにくい。
つい相手に気を遣いすぎてしまって、ぐったり…
さらに、そんな自分にモヤモヤして「もう嫌だ😭」となっちゃうことってありませんか?
- Noと言うのが苦手
- つい人の顔色を窺ってしまう
- 気を遣いすぎて疲れる
- 人の影響を受けやすい
- 自分よりも他人を優先しがち
- よく人に対してイライラしてしまう
こうした傾向を、
自分は、そういう性格だから仕方ない。
そう思ってきた方も多いかもしれません。
でも、それってあなたの「性格のせいじゃない」かもしれないんです。
実はそこには、
「境界線(バウンダリー)」の問題が存在している可能性があります。
今回のテーマは、人間関係において重要な、この「境界線」についてです。
- 境界線(バウンダリー)って、そもそも何?
- 「やっちゃいがち」な境界線の落とし穴
- 境界線をうまく引けない理由
- 私自身が気づいた境界線の弱さ
- 境界線は実は「身体の感覚」
- 実際に試せる境界線のワーク
これらの内容と、実際に境界線を育んでいくために重要な「身体の感覚」について、身体心理セラピストがお伝えしていきます^^
境界線とは「人間関係で大切な“見えない線”」
まず、境界線(バウンダリー)とは、ざっくり言えば、
「自分の領域」と「他人の領域」を分ける“見えない境界線”のこと。
もう少し具体的に言うと、
どこまでが自分の責任で、どこからが相手の責任なのか。
どこまで相手に関わり、どこから距離を取るのか。
自分の時間・感情・価値観・身体的スペースなどを、どのように守るのか。
こうした「自他の領域の区切り」のことを、心理の世界では「境界線(バウンダリー)」と呼びます。
人間関係のストレスの多くは、この境界線を越えたり越えられたりしたときに起こるのです。
境界線が曖昧だと、人間関係がしんどくなる。
日常で、こんな風に思ったりすることがありませんか?
●「私がこれだけやってあげたのに、感謝してもらえない」
●「相手の気分を害したくなくてNoが言えない」
●「あなたのためを思って言ってるんだ」
●「もっと理解してくれてもいいのに!」
これらは一見、「優しさ」や「当然のこと」のように思えるかもしれません。
でも実は、相手の領域に踏み込んでしまっているサインだったりします。
なぜなら、その人の感情や選択、人生の責任は、あくまで「その人自身のもの」。
どんな感情を持つか、どう生きるかは、その人の自由であり責任なのです。
境界線が曖昧になると、
相手に踏み込みすぎて巻き込まれたり、
逆に相手から過度な干渉を許してしまい、疲れてしまう。
こうした人間関係のストレスは、多くの人が経験していることではないでしょうか。
「境界線って、分かってても難しい!」というあなたへ。
とは言え、実際は、「自分の領域」と「相手の領域」とを明確に分けるのって、難しいですよね😂
特に家族なんて、お互いの境界線を越えたり踏み込まれたり、そんなのはもう日常茶飯事、当然のことです😅
単純に「境界線を引きさえすればいい」というものではないし、
境界線を引くラインに「絶対的な正解」があるわけでもありません。
どこで境界線を引くべきか。
それが難しい問題なんですよね😂
だからこそ、こんな疑問や迷いを持ってしまいがちです。
「境界線を引けって言うけど、どこで引けばいいの?」
「相手と距離を取るのが正しいの?」
「でも、冷たい人にはなりたくない…」
「境界線を引くライン」のヒント
大切なのは、
「正しさ」や「こうするべき」で考えるのではなく、
“今の自分の状態”を軸にして境界線を考えることです。
その基準について、尊敬する先輩の言葉で、私が深く納得したのがこれです。
自分の元気(健康)と機嫌を守れるか?
それを基準に境界線を考える。
たとえば、
友人から遊びに誘われたとき、疲れていて、機嫌や体調が悪くなりそうだったら断る。
頼まれごとをした時も「自分の元気(健康)と機嫌を守れるか」を基準に考えてみる。
この基準はとてもシンプルですが、分かりやすく役に立つ指標だと思います^^
その時々で「適切な境界線」は変わる。
ここまで見てきたように、「境界線を引く場所は、時と場合によって変わる」ということ。
機械的に、そして完全に自他の領域を分けてしまうと、人間関係は硬直して、不自由なものになってしまいます。
相手が困っている時に、「それはあなたの問題だから」と距離を置くことが、必ずしも「適切な境界線」ではないわけです。
状況や関係性、自分自身の状態によって、「適切な境界線」は変わります。
例えば、頼みごとをされたとき、正直イヤだけど、相手との関係や状況によっては、「どうしても断れない」「引き受けなきゃいけない」こと、ありますよね。
そんなとき、「境界線」について単純に考えてしまうと、
「境界線に侵入されてるんだから、頑張って断らなきゃ😭」と思ってしまったりしますが、
それが必ずしも適切なわけではありません。
「嫌だけど、今回は“自分の責任において”引き受ける。」
そういう選択が必要な時もあります。
ポイントは、「嫌だけど、自分が選んで引き受けた」ということ。
私たちはこういう状況では、つい頼みごとをしてきた相手を悪者にしてしまったりしますが😅
でも、引き受けたのは自分。
「今回は、断るよりも引き受けた方がマシ」という選択を「自分が」したわけです。
「本当は嫌だったのに…」
「あの人に振り回されてる…」
と相手を責めるのではなく、
「嫌だけど、今回は“自分の責任で”引き受けた」
そんな風に、「自分で選んだ」と思えるだけで、気持ちのしんどさは、少し違ってきたりします。
「分かっていても難しい」という時。
こんな風に、境界線に、「常にここで引くべき」みたいな、「絶対の正解」はありません。
- 完璧に線引きすればいいわけでもない
- 常に距離を取るのが「正しい」わけでもない
「適切な境界線」というのは、状況や関係性によって、柔軟に変わるものです。
…と、これまた「分かっていても難しい😭」となったりしますよね💦
それは何故かを見ていってみましょう。
境界線は「知識」ではなく「身体の感覚」
「分かっていても、境界線を引くことが難しい…」となってしまう理由、
そのひとつが、
「境界線」には、
概念…つまり考え方や知識だけではなく、
「身体の感覚」が深く関わっているからです。
たとえば、
頭では大丈夫と思っていても、
身体は怖がっている。
そんな経験は無いでしょうか?
これは、頭の考えと身体感覚の間にギャップがある状態です。
境界線も同様で、
身体のレベルで境界線を感じられていないと、どんなに理屈で「境界線を引こう」と思っても、実際には難しいのです。
「境界線を引こう」と思っても難しい時は、この「身体感覚としての境界線」を見ていくことが役に立つ場合があります。
幼少期の環境やトラウマの影響
そもそも「境界線が無い」、もしくは「境界線が薄い」という場合があります。
境界線の感覚は、多くの場合、幼少期の生育環境の中で無意識に学習されます。
幼少期に「適切な境界線を引く」という学習ができなかった場合、
例としては、
✅怒り・不機嫌・脅威を持った養育者との関係性の中で、境界線が侵されるのが日常だった
✅意識が常に脅威に向いていて、自分の身体や感覚を感じられなかった
✅「自分のスペースを守ってもいい」という選択肢が存在しなかった
こうした状態では、
自分の領域、つまり「境界線の感覚」を持てなかったり、
「境界線を引く」=「危険・関係が壊れる・愛されなくなる」などと学習されてしまうことがあります。
また、子どもの頃に境界線の感覚を得られていても、
トラウマ体験や事故などで境界線が破れたようになったり、薄くなったりすることもあります。
このように、
境界線の感覚というのは、
「身体が無意識に学習」したもの。
だからこそ、「どうしても境界線を引くのが難しい…」とか「どこで境界線を引いたらいいか分からない」という場合、
それは、
性格の問題ではなく、
この「身体的な境界線の感覚」が影響している可能性があるのです。
生まれ持った気質や文化的な影響もある。
ここまでは、幼少期の環境やトラウマに焦点を当てて説明をしてきましたが、
「適切な境界線が引けない」原因は、必ずしもトラウマだけに起因するわけではありません。
実際には多様な要素が絡み合っています。
境界線の感覚は、生まれ持った気質(例えばHSP)や、人生の中での様々な出来事、経験からも影響を受けます。
また、文化的・社会的背景(例えば、和を重んじる価値観や、上下関係を強く意識する文化など)も、境界線の形成に大きく影響を及ぼす場合があります。
日本には、自他の境界が曖昧なのを良しとされる傾向があります。
相手をケアすること。
相手の問題を引き受けること。
個人の意向よりも和を大切にして、はっきり意見を言わないこと。
こうしたことが美徳とされる価値観がありますよね。
こうした中では、はっきり境界線を引いたり、自分の意見を言ったりすることは「危険」や「不調和」に結びくこともあるため、一般的に、日本人は境界線の感覚が弱いと言われることがあります。
もちろん、これは決して悪いことではありません。
こうした面は、日本人の優しさや調和を大切にする穏やかな性質の表れです。
境界線が曖昧でも、特に苦しくなければ、問題はありません。
けれども、人間関係や境界線の問題でストレスや苦しさを感じる場合には、境界線について考えてみることは、楽になるためのヒントや助けやになるかもしれません^^
「境界線の感覚」は、育てられる。
「自分がお留守」状態になっていた。
私は、自分の意見を言うことにあまり苦手意識が無く、どちらかというと、自己主張が強い方かもしれません(^^;
なので、「私は境界線はしっかりしている」と思っていました。
けれどもある時、自分が、相手の機嫌に巻き込まれていること…
相手の機嫌が悪そうな時に、私が何とかしなければならないような感覚があることに気付きました。
身体に緊張感がある。
「このままじゃマズイ」という、どこか切羽詰まった感じがある。
自分がそんな状態になっていると気付いたのです。
そこから自分なりにワークを重ねて見えてきたのは、
相手が不機嫌そうな時や困っていそうな時、私は、意識がほとんど相手の機嫌や表情に集中していて、
「自分がお留守」状態になっていたこと。
また、
「自分を守ってもいい」
「相手の影響を受けなくてもいい」
そういう感覚が、私の中にまったく存在していなかったということでした。
そして、「自分を守ってもいい」という感覚を、身体の内側で少しずつ感じることをしていくうちに、
「完全に自分がお留守」の状態から、少しずつ自分の方にも意識が向くようになっていきました。
その結果、以前よりも相手の感情に巻き込まれず、
自分自身を感じながら、自分を守る感覚が少しずつ育っていったのです。
脅威に対して能動的に対処しようとする、つまり「自分が何とかしようとする」反応は、交感神経系の防衛反応の一つです。
このとき、身体はすぐに動けるよう筋肉を緊張させ、目は脅威の対象(この場合は相手の不機嫌な様子)に集中して視野が狭くなります。(この状態を、私は「自分がお留守」のように感じたということです。)
私たちの身体もまた、脅威を感じるときには、こうして反応しています。
「境界線」は、学習できる。育てられる。
私の例を挙げましたが、こんな風に、「境界線の感覚」は、学習し、育てていくことができます。
先にお伝えしたように、境界線にはさまざまな要素が絡みあっているために、自分の境界線の状態に気づき、そして育てていくためには、
その方に合わせて、色々な角度からのアプローチやワークが必要になります。
もしこの記事を読んで、
「まさに今の自分のことだ…」
「頭ではわかるけど、どうしても境界線を引けない」
そんな風に感じた方は、ぜひセッションを活用してみてください。
あなたにとっての「自分らしい、無理のない境界線の感覚」を、一緒に育んでいきましょう^^
「境界線を引く=危険」と感じてしまう場合がある。
まずは第一歩として、自分でできるセルフワークとしてお勧めしたいのが、「今の自分の境界線の感覚」を知ってみること。
このブログの最後で簡単なワークをご紹介するので、ご興味のある方はやってみてくださいね^^
なお、人によっては、「境界線を感じること」や「境界線を引くこと」に強い抵抗を感じる場合もあります。
特に、境界線を引くことが許されなかった環境で育った方は、「境界線を引く=危険」と感じてしまうこともあります。
抵抗などを感じる場合は、無理をせずに、ぜひ専門家のサポートを受けることをおすすめします。
「この世界の中で、どんな自分で在るか」に繋がっていく。
境界線の感覚というのは、思っている以上にとても複雑だったりします。
そして同時に、すごく探求しがいのあるものです。
境界線のテーマは、
単なる人間関係にとどまらず、
”この世界の中で、どんな自分で在るか”ということに繋がっていくからです。
いやあ、人間て、本当に奥が深いですね!
境界線の感覚を探求することは、
自分自身を深く知り、自分らしさや安心感を育むことにも繋がります。
焦らず、自分のペースで取り組んでいきましょう😊
もし「もっと深く探求したい」「一人では難しい」と感じる方は、ぜひセッションをご活用ください。
安心して取り組めるサポートをご提供しています。
自分でできるセルフワークのご紹介
では最後に、「今の自分の境界線の感覚」を知るためのセルフワークをご紹介します。
「今の自分の状態」を知ることが、境界線を育んでいくための大切な最初の一歩です。
「身体で感じる安全な境界線の感覚」を、ぜひ体験してみてくださいね^^
目は開けても閉じても、心地良い方でOKです。
楽に立った姿勢で始めましょう。
1.まずは、自分の身体の感覚に意識を向けてみましょう。
地面や床に触れている足の感覚、身体の重さ、呼吸などに気づけるでしょうか。
まずは今の身体の状態や感覚に気づいてみましょう。
2.次に、自分の皮膚に意識を向けてみましょう。
皮膚は、自分と外の世界を分ける「境界線」でもあります。
皮膚の感覚、自分の身体、そして外の世界を感じられるでしょうか。
自分の皮膚の存在を、手の指でタッピングしたり、手のひらで触れたりして確かめてみましょう。
3.そうしたら、いわゆる「パーソナルスペース」を感じてみましょう。
動物には「縄張り意識」があると言われますよね。
人間にもそれと近い感覚があります。
パーソナルスペースは、「自分の領域」とも言える身体からある一定の空間で、そこに侵入されると不快に感じることもあります。
今の自分のパーソナルスペースは、どれくらいの広さでしょうか。
手を伸ばしたり、身体を動かしたりして感じてみましょう。
ちなみに、パーソナルスペースは常に一定ではありません。
これも、状況や相手によって変化します。
4.最後に、そのパーソナルスペースを、安全に心地よく守ってくれるものをイメージしてみましょう。
現実に存在するものでもしないものでも、どんなものでもOKです。
自分の感覚を感じながら、好奇心を持って、「どんなものが心地よさや安心を感じられそうか?」を探ってみましょう。
- 透明のシャボン玉のような膜
- 虹色の壁のようなもの
- 美しい鳥かごのようなもの花畑や、
- 光輝く蚕の繭などなど…
そのパーソナルスペースを安全に心地よく守ってくれるものがあると、どんな感じがするでしょうか?
心地よさや安心感があれば、その感覚を身体でよく味わって、終了します。
▼以下の音声ガイドもご参考に♪